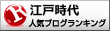さてさて、前回、
「江戸の男はどうして顔が板から離れなくなってしまったのでしょうか?」
というご質問を皆さんにしました。
普通に読めば、「1、伊勢大神宮の罰」なんですが、これはあくまで宿屋の主人が言っているだけです。
しかも、男のエッチな行為への罰ならば、同罪で隣の男女も罰を受けるはずですが、隣の男女が罰を受けた形跡はありません。
この疑問を解くヒントは、本編の最初の部分にあります。
ほら、この男が住んでいるのは江戸の葺屋町《ふきやちょう》って書いてありましたよね。
葺屋町ってどういう場所だかご存知ですか?
葺屋町は当時、芝居小屋があった場所です。
歌舞伎若衆は昼は舞台に立ち、夜は色を売っていました。
つまり、芝居小屋があった葺屋町は、男色の町だったのです。
男が「裏住《うらずみ》(裏通りに住んでいる)」というのも、冒頭にあった「裏へ回れば衆道の神」というのを踏まえているのでしょう。
そうそう、説明するのを忘れていましたが、この冒頭にあった
「これが女道《にょどう》の神、裏へ回れば衆道《しゅどう》の神」
という部分、なんで「裏に回れば」ってわざわざ言っているかわかりますか?
女色は前の穴を使って、男色は裏(後ろ)の穴を使うからです、いやんヾ(๑╹◡╹)ノ"
このお話が収録されている『野傾友三味線』という本は、男色と女色を両方扱っているので、両色の神をわざわざ登場させたのでしょう。
そして、隣の様子に興奮した男が押さえつけたイチモツのたとえに使われた「火吹竹」は、「お釜」の火を起こすために使われたものです。
「お釜」が何の隠語かは、言わなくても分かりますよねヾ(๑╹◡╹)ノ"
男の職業は葺屋町に住んでいることから、本文中には書かれていませんが、おそらく芝居に関って収入を得る何らかの職業だったと思われます。
つまり、男色の恩恵を受け、男色のために精進すべき男が、こともあろうに男女のチョメチョメ(女色)を見て興奮したので、伊勢神宮というより、その末社の「衆道の神」の怒りに触れたのではないでしょうか?
ちなみに色を売る役者のランクで上位の者を「板付《いたつき》」と言いました。
男色のことを思い出せとばかりに、板を張り付かせたのかもしれません。
というわけで、私の見解は、「4、衆道の神の罰」でしたヾ(๑╹◡╹)ノ"
「5、江戸男の罪悪感」も無きにしもあらずですが、罪悪感があったら、あそこまでして覗かないと思ったのでw
うわあん、板が取れなくなっちゃったよ~ヾ(๑╹◡╹)ノ"
どうしてそうなったヾ(๑╹◡╹)ノ"
◆北見花芽のほしい物リストです♪
◆インフォメーション
井原西鶴の大著、『男色大鑑』の一般向けの現代語訳「武士編」及び「歌舞伎若衆編」が発売中です♪
北見花芽の中の人もちょっと書いてるので、興味のある方も無い方も、下のアマゾンリンクから買ってくださると狂喜乱舞します♪
※ 書店で買っても、北見花芽の中の人には直接お金が入らないので何卒。

- 作者: 染谷智幸,畑中千晶,河合眞澄,佐藤智子,杉本紀子,濵口順一,浜田泰彦,早川由美,松村美奈,あんどうれい,大竹直子,九州男児,こふで,紗久楽さわ
- 出版社/メーカー: 文学通信
- 発売日: 2019/10/21
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログを見る
『男色を描く』も合わせてお読みいただけるとより楽しめると思いますよ♪
※ こちらも北見花芽の中の人がちょっと書いていますので。
◆北見花芽 こと きひみハマめ のホームページ♪
◆拍手で応援していただけたら嬉しいです♪
(はてなIDをお持ちでない方でも押せますし、コメントもできます)
◆ランキング参加してます♪ ポチしてね♪
◆よろしければ はてなブックマーク もお願いします♪ バズりたいです!w