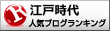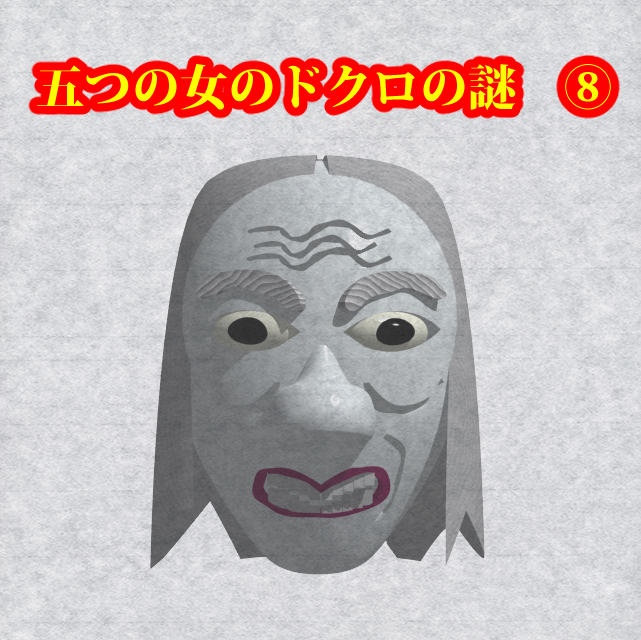
さあ、いよいよ、「五つの女のドクロの謎」を解き明かしますよ!ヾ(๑╹◡╹)ノ"
前回までに、
井原西鶴[※以下「西鶴」]『本朝桜陰比事』(元禄二[一六八九]年刊)巻四の七「仕掛物は水になす桂川」[※以下「仕掛物」]
と
西村市郎右衛門[※以下「西村」]『御伽比丘尼』(貞享四[一六八七]年刊)巻四の五「不思議は妙、妙は不思議」[※以下「不思議は妙」]
の二作品を読みました。
「仕掛物」より「不思議は妙」の方が先に書かれたんだね。
この二作品には共通するワードが出てきます。
主要人物の名前:
「里人の何がし」(「仕掛物」)、「何がしとかや言える士」(「不思議は妙」)
事件が起こった状況:
「都の町、静かにして」(「仕掛物」)、「何となく世上静かなるに」(「不思議は妙」)
物語のカギとなるアイテム:
「年久しき瀑首《されこうべ》五つ、女の黒髪入り乱れし」(「仕掛物」)
「女首五つ、黒き髪を乱し」「女の首、一時に髑髏《されこうべ》とぞなりける」(「不思議は妙」)
特に、「黒髪の女のシャレコウベが五つ」というのは、とても偶然の一致とは思えません。
じゃあ、西鶴が西村をパクったんだね。
まあ、ここだけ見れば、そういう風に思えるかもしれないけど、まだ話が途中、話を最後まで聞きなさい。
そもそも、井原西鶴『好色一代男』が登場する以前の小説は、仮名草子と言って、内容は教訓性が強く説教じみたものが主でした。
ところが、井原西鶴が書いた『好色一代男』(天和二[一六八二]年刊)は、当時の世相を取り入れた、娯楽的要素が強い楽しい作品です。
『好色一代男』の大ヒットにより、これ以降、他の作家も西鶴の生み出した形式に追随し、この時代の小説のジャンルは仮名草子から浮世草子と呼ばれるものに変貌します。
要は、この時期の小説は西村も含め、ほぼ西鶴の模倣という訳です。
じゃあ、西村が西鶴をパクったんだね。
だから、話を最後までちゃんと聞きなさい。
西村市郎右衛門が作者や出版者としてかかわった一連の作品を西村本と言います。
西鶴と西村は同時代で、ライバル関係と言うか敵対関係にありました。
両者はお互いの作品の動向を注視し、情報戦のようなものまで繰り広げていたようです。
たとえば、西鶴は、
西村が『宗祇諸国物語』(貞享二[一六八五]年刊)という作品を出版する情報をキャッチして、
『西鶴諸国はなし』(貞享二[一六八五]年刊)というソックリなタイトルの作品を出版すると、
西村は、
西鶴の『好色一代男』『好色二代男(諸艶大鑑)』(貞享元[一六八四]年刊)というタイトルを模倣した
『好色三代男』(貞享三[一六八六]年刊)という作品を出版したり。
西鶴が西村をパクって、西村が西鶴をパクって???
なんだかよくわかんなくなってきたヾ(๑╹◡╹)ノ"
だから、まだ説明が途中だってば!
そもそも西村は「五つの女の首(ドクロ)」という発想をどこから得たんだろうね?
「男の首」でも、「二つ」や「三つ」でも良かったのに。
何か実際にそういう事件でもあったのかな?
目の付け所は悪くない。
「五」「女」で何か思い当たる事はない?
「五」「女」、、、五人組の女性!ゴールデンハーフ!ヾ(๑╹◡╹)ノ"www.youtube.com
(ガン無視)
そう、「五」「女」と言えば、『御伽比丘尼』の前年に刊行された西鶴の代表作『好色五人女』(貞享三[一六八六]年刊)が、当時の読者にも思い浮かんだことでしょう。
「不思議は妙」における五つの女の生首は、西鶴を表していると思われます。
西鶴の首を取ってやるという西村の決意表明とでも言えるのです。
「たった今、切り捨てられたような、女の生首が五つ」(「不思議は妙」)
→西鶴作品の人気と斬新さをたとえているのでしょう。
「女の生首は一瞬でシャレコウベになったのでした」(「不思議は妙」)
→ですが、西鶴の人気なんて一時的なもので、すぐになくなると言っているわけです。
「女の生首という怪異を起こしたのは、魔道の祈祷です」(「不思議は妙」)
→西鶴は魔道ということになります。
「魔道と仏道は異なる道ですが、心を込めて念ずると言う点においては同じです」(「不思議は妙」)
→ということは、西村は仏道。一見、共存しようと呼び掛けているように見えますが、、、。。
「魔道と仏道、どうせ念ずるなら、魔道はやめて、ひたすら仏道に励んだ方が良いに決まっています」(「不思議は妙」)
→どうせ読むなら西鶴より西村を読もうと読者に呼びかけているのですヾ(๑╹◡╹)ノ"
要するに、直接名前を出すわけにもいかないから、当時の読者には分かるように、怪談話に見せかけて西鶴をディスってるわけだね。
それに気づいた西鶴が書いたのが「仕掛物」というわけです。
五つの女のドクロは、西村は西鶴を表していましたが、ここでは「不思議は妙」に書かれている内容、つまり西村本の事を表しています。
「新しい長持に、女の黒髪と古いシャレコウベが五つ入っていました」(「仕掛物」)
→西村は、西鶴が確立した新しい浮世草子と言う形式で作品を作っていますが、中味は前時代の仮名草子のような、古い説教臭い内容のままであると批判しているわけです。
「『このたび桂川を流れた長持の話題を、浄瑠璃や歌舞伎に取り入れたら、厳しく処罰する』と、芝居小屋の連中にしっかり触れ回ってこい」(「仕掛物」)
→「二度と俺の作品をディスるんじゃねえぞ!」という西鶴の怒りが込められているのでしょう。
「仕掛物」は、西鶴作品の中でも、異常に短い作品なんですよね。
おそらく、西村に反論するためだけに、ちゃっちゃっと書いたのでしょう。
要するに、西村が「不思議は妙」で西鶴をディスったけれど、西鶴に「仕掛物」でディスり返されたというわけだね。
なんか、どっちもどっちのような気もするけど、結局の所、本当に怖いのは、化け物よりも、水面下でディスりあう人間の方だというねヾ(๑╹◡╹)ノ"
で、西鶴と西村の争いはその後どうなったかというと、言うまでもありませんが、西村は西鶴には勝てず、廃れて行ったのでした。
なるべく、簡潔に書いたつもりなんですが、ちょっと長くなってしまいました。
以上、北見花芽の妄想でしたヾ(๑╹◡╹)ノ"
信じるも信じないも三つ目次第!ヾ(๑╹◡╹)ノ"
※まだ次回に続きます。
①~⑦まで、まだお読みでない方、読み直したい方は、こちらからどうぞ。
kihiminhamame.hatenablog.com
kihiminhamame.hatenablog.com
◆北見花芽のほしい物リストです♪ 5月3日は北見花芽の誕生日♪
◆インフォメーション
井原西鶴の大著、『男色大鑑』の一般向けの現代語訳「武士編」及び「歌舞伎若衆編」が発売中です♪
北見花芽の中の人もちょっと書いてるので、興味のある方も無い方も、下のアマゾンリンクから買ってくださると狂喜乱舞します♪
※ 書店で買っても、北見花芽の中の人には直接お金が入らないので何卒。

- 作者: 染谷智幸,畑中千晶,河合眞澄,佐藤智子,杉本紀子,濵口順一,浜田泰彦,早川由美,松村美奈,あんどうれい,大竹直子,九州男児,こふで,紗久楽さわ
- 出版社/メーカー: 文学通信
- 発売日: 2019/10/21
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログを見る
『男色を描く』も合わせてお読みいただけるとより楽しめると思いますよ♪
※ こちらも北見花芽の中の人がちょっと書いていますので。
◆北見花芽 こと きひみハマめ のホームページ♪
◆拍手で応援していただけたら嬉しいです♪
(はてなIDをお持ちでない方でも押せますし、コメントもできます)
◆ランキング参加してます♪ ポチしてね♪
◆よろしければ はてなブックマーク もお願いします♪ バズりたいです!w